エレベーターの前で立ち話をしていた
ときのこと。
「うち、もう限界だわ。雨漏りも
ひどくなってきたし…」と、
上の階の奥さんがぽつり。
築40年を超えた我がマンション。
見上げればひび割れた外壁、軋む階段、
変色した廊下の床。
誰もが「そろそろ限界」と感じていた
——でも、建て替えの話はいつも、
立ち消えになる。
なぜ、私たちは一歩を踏み出せなかった
のか。
住民の願いと現実のギャップ
最初に「建て替え」の話が出たのは、
4年前の管理組合総会だった。
「このままでは資産価値が下がる一方
です」
「新しいマンションになれば、将来の
売却にも有利です」
理事長の説明に、会場は一瞬、
ざわめいた。
「でも…お金はいくらかかるん
ですか?」
提案されたのは、
一人あたり2000万円の負担。
——その瞬間、空気が変わった。
高齢住民にとっての“2000万円”の重さ
「うちは年金暮らしだから無理ですよ」
「70過ぎてローンなんて、通るわけ
ないじゃないですか」
——そんな声が続出した。
視覚的にはキレイな完成予想図が
スライドに映し出されていたが、
その“夢の光景”が、遠くぼやけて
見えた。
私も夫と家に帰り、電卓をたたいた。
老後資金、子どもの結婚資金、
車の買い替え…
「2000万円?そんな余裕ないよな」
と、夫は静かに言った。
数字は冷たく、心の中に重く
のしかかる。
仮住まいの不安と心の負担
建て替えには、最低でも1年の仮住まい
が必要。
「荷物を全部出すの?」
「引っ越し先、ペット可の物件なんて
ある?」
年配の方は特に、変化を受け入れる
体力も気力も残っていない。
ある日、同じマンションに住む高齢女性
が泣きながら話してくれた。
「私はね、この部屋で主人と最後まで
過ごすって決めてたの。見知らぬ部屋
で最期を迎えるなんて考えられない…」
その言葉に、何も返せなかった。
話し合いの末、私たちが選んだ“現実”——でも、答えはまだ出ていない
最終的に、建て替えの話は見送り
となった。
必要な賛成数には届かず、
「当面は修繕で対応しよう」
という方針に落ち着いた。
しかし、それは「反対の声が悪」
だったからではない。
高齢、収入、家族の事情
——それぞれが自分の暮らしを守る
ために出した精一杯の判断だった。
管理組合は方向転換し、修繕計画の
見直しに動き出した。
「できることを、できる範囲で」
それが、今の私たちにできる現実的な
選択だった。
——ただし、それは“最終的な答え”
ではない。
もし南海トラフのような大規模地震が
起これば、修繕で延命しただけの今の
建物では限界がある。
倒壊や避難生活のリスクを考えると、
将来的には建て替えという選択を
避けては通れないかもしれない。
いまはまだ、
“答えが出たようで出ていない”、
そんな宙ぶらりんな状態だ。
私たちは今後も、避けては通れない
課題と向き合い続けていかなければ
ならない。
まとめ
マンションの建て替えは、資産価値の
向上や安全性の確保といった
「理想の選択」に見えるかもしれ
ません。
しかし現実には、住民一人ひとりの
事情や、経済的・身体的な負担が立ち
はだかり、すぐに決断できるものでは
ありません。
私たちは今回、「修繕でつなぐ」
という現実的な道を選びました。
でも、それはあくまで“延命”であり、
“根本解決”ではありません。
南海トラフ地震のような、いつ起きても
おかしくない大規模地震にこの建物が
耐えられるのか?
もし耐えられなかったとき、私たちは
仮住まい先もなく、財産も失い、路頭に
迷うことになるかもしれない。
今の選択は、決して「答えが出た」
わけではないのです。
将来の安心を本当の意味で手に入れる
には、いつか必ず、建て替えという現実
から逃げずに向き合う必要がある。
それを忘れずに、次の世代にも語り継い
でいくべきなのだと思います。

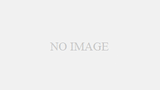
コメント